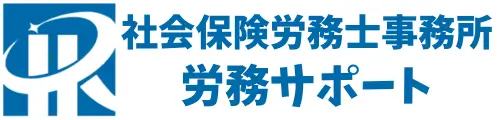今後の雇用政策の方向性について
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 政府の雇用対策研究会は、中長期的な観点を含めた今後の政策の具体的な方向性について報告書を取りまとめました。参考ページ https://www.mhlw.go.jp/stf […]
労働者 死傷病報告書の電子申請が義務化
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 令和7年(2025年)1月1日以降に報告される労働者死傷病報告については電子申請による報告が義務化されます。 労働者死傷病報告の改正 これまで自由記載であった①、②、③、 […]
遺伝情報による不当な差別についてのQ&A
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 ゲノム情報は、生物の遺伝情報の全体をさし、病気の診断や治療、予防への活用が期待されます。例えば、東京大学とNTTによるゲノム情報を活用した生活習慣病予防に関する共同研究が […]
【2024年10月~】社会保険が適用拡大されます
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 2024年10月1日からは、常時100人超から、さらに常時51人以上と要件が見直され社会保険に加入する短時間労働者が一層増加します。この機会に社会保険の適用拡大について、 […]
コロナ前後の働く人の意識変化は?テレワーク実施率、微増
名古屋市の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 2023 年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症の区分が「5類感染症」となり国のコロナ対策は大きな節目を迎えました。 日本生産性本部の「働く人の意識に関する調査 […]
「技能実習制度」約7割が法律違反・・・
名古屋市の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 2024年6月に「育成就労制度」の創設が決定されました。 育成就労制度は、「技能実習」に代わる在留資格として特定技能1号水準の人財の確保のため導入されます。詳細はこちら […]
違法な時間外労働、2023年度は1万超
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 厚生労働省は7月に、2023年度に長時間労働が疑われる2万6117事業所を対象とした監督指導結果を公表しました。 違法な時間外労働 時間外・休日労働時間数が1か月当たり […]
過労死を防止しましょう
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 過労死等の事案による労災の請求件数は増加傾向にあり長時間労働対策に加え、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策の重要性が一層増しています。 政府は2024年8月、「過労 […]
賃金のデジタル払い~資金移動業者を初めて指定
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 賃金のデジタル払い 賃金の支払い方法については通貨のほか、労働者の同意を得た場合には銀行その他の金融機関の貯金または貯金の口座への振り込みなどによることができます。 これ […]
2024年8月~雇用保険の基本手当の額等について
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 雇用保険の基本手当は、「賃金日額」に基づいて算定されます。賃金日額については上限額と下限額を設定しており「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。 […]
『カスハラ』~企業ができる対策は?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 帝国データバンクは「カスタマーハラスメントに関する企業の意識調査」を発表しました。この内容で、カスハラの実態を確認しましょう。 カスハラの実態 直近1年以内に従業員がカス […]
「働き方改革」から5年、定着状況は?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 時間外労働の上限規制の導入や、年次有給休暇の5日の取得を義務化を柱とする「働き方改革関連法」が2019年4月に成立してから、5年経過しました。 2024年7月、日本労働組 […]
出産後の働き方は4パターン!共働き夫婦の収入はいくら?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 2024年1月、東京都産業労働局が、妻の出産後の働き方で世帯収入がどう変わるかを、まとめました。 この試算では、同い年の夫婦で22歳で正社員として入社し、妻が31歳で出産 […]
中小企業の賃上げ、政府の対策は?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 近年、賃上げの流れが続いています。昨年の最低賃金の全国加重平均は1,004円と、「全国加重平均1,000円」を達成しました。引上げ額は全国加重平均43円で、過去最高の引上 […]
中小企業における賃金動向
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。日本銀行は12日、地域経済報告-さくらレポート(別冊シリーズ)を発表しました。日本銀行「地域経済報告―さくらレポート―(別冊シリーズ)」 副題は「地域の中堅・中小企業におけ […]