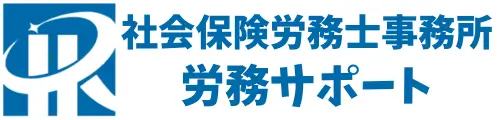社労士
職務給を導入するポイントは?
名古屋の社労士事務所、労務サポートです。 ジョブ型賃金については知りたい方は、以下の記事をご覧ください。「ジョブ型人事」なぜ注目される?導入目的と方法をご紹介」 職務給を導入するときに、参考となる調査をご紹介します。 職 […]
ビジネス視点で考える!企業の人権尊重とは?
SDGsは2030年までに持続可能なよりよい世界を実現する国際目標です。
その17の目標のうち、14が「人権」に関する目標で、社労士の分野でもあります。
SDGsの本質は、人権を尊重するビジネスを行うことにあります。
SDGSについて興味のある方は、こちらをご覧ください。
年収の壁の対策とは?キャリアアップ助成金の新コース!
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 中小企業では、人手不足への対応が急務となっています。政府は、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため2023年10月から、以下の3つの […]
注目の「病気休暇」とは?
名古屋の社労士事務所の労務サポートです。 厚生労働省は「病気休暇」についての理解を促進するために「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しました。 加えて病気休暇に関するリーフレットを作成しています。 病気休暇とは? […]
マイナンバーが健康保険証と一体化!2024年秋から早く簡単な手続きへ
名古屋の社労士事務所、労務サポートです。 健康保険証は、日本国内に在住するすべての人が持つ必要がある保険証であり、医療機関での受診や薬局での薬の受け取りなどに必要です。 ここでは2024年以降のマイナンバー保険証はどうな […]
御社の採用は大丈夫?お金をかけない採用方法をご紹介。
名古屋の社労士事務所、労務サポートです。新年あけましておめでとうございます。今年も皆様にお役に立つ情報を提供していきたいと思っています。今回は「採用」についてです。 少子高齢化はどれくらい進んでいますか? 2022年成人 […]
健康保険の扶養とは?社労士が解説!
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。 さて扶養には所得税と健康保険の2種類があります。今回は健康保険の「扶養」について解説していきます。 扶養の対象者とは? 扶養といえば、夫が妻や子供を扶養するイメージがあり […]
有給休暇の基本について社労士が解説【知っトク労働法⑧】
こんにちは。名古屋市の社会保険労務士事務所 労務サポートです。労務相談の中で有給休暇に関する相談が多いです。知って得する労働法8回目は、有給休暇の基本について社会保険労務士が解説します。 有給休暇の基本条件 有給休暇は労 […]
人材力を高めるリカレント教育!大人の学び直しの進め方
リカレント教育とは? リカレント教育の背景 日本でリカレント教育が重要視され始めている理由は、デジタル化と職業人生の長期化です。学校を卒業し、働きつづけ、リタイアする従来の流れは通用しなくなってきています。 国としてもリ […]