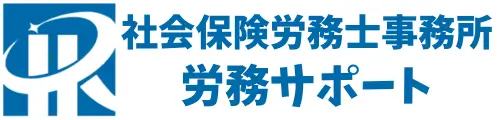「生成AI、業務利用は5割超」—急拡大の裏で課題となる「ルール不在」のリスク

日経BP総合研究所の最新調査により、日本企業の半数以上(54.5%)が
すでに業務で生成AIを利用していることが明らかになりました。
約3割の会社が、AI利用ガイドライン策定済み
「生成AIの利用にあたってガイドラインを策定済み」と答えたのは38.7%にとどまり
「準備中」が6.8%と、まだ十分に整備が進んでいない実態が明らかになっています。
技術の進化が速すぎてルール策定が追いつかないのが現状です。
この「利用先行、ルール後追い」の現状は
今後のトラブル発生リスクをはらんでいると言えるでしょう。
また、生成AIを活用した新規ビジネスについては
すでに「立ち上げ済み」が7.7%、「準備・検討中」が7.5%
「立ち上げる可能性がある」とする企業は21.1%に達しました。
3分の1強にあたる36.3%が5年後までに生成AIを活用したビジネスを
新規に立ち上げている可能性があるという結果を踏まえると
生成AIを活用したビジネスの立ち上げは待ったなしの状況と考えることもできそうです。
経営者が押さえておくべきリスクと対応
生成AIの導入は、業務効率化や新規ビジネスの創出につながる一方で
以下のような法的リスクがあります。
- 個人情報・機密情報の取り扱い:
従業員が顧客データや開発中の新製品情報などを生成AIに入力することで
意図せず情報漏洩を招くリスクがあります - 著作権・知的財産の侵害リスク:
出力された文章や画像が既存の著作物と類似し
知らずに著作権侵害を引き起こす可能性があります。 - 労務管理上の公平性や評価制度への影響:
そのアルゴリズムの透明性が問題となり
評価の公平性が担保されない可能性があります。
特にガイドラインの未整備は
トラブル時に「従業員の責任か、会社の責任か」が曖昧になる要因となりかねません。
社労士ができるサポート
生成AIは、業務の生産性を劇的に向上させる強力な武器です。
しかし、その力を最大限に活かすためには、「リスク管理」という土台が不可欠です。
適切なガイドラインを策定し、従業員が安心してAIを活用できる環境を整えることこそ
デジタル変革時代を勝ち抜くための重要な経営判断と言えるでしょう。
労務サポートでは
- 生成AI利用に関する社内ルール(ガイドライン)の策定支援:
AI利用の目的、使用範囲、入力・出力データの管理方法、トラブル時の報告フローなど - 情報管理体制や就業規則への反映:
AI利用に関する規定を追加し、法的根拠を明確にします。 - 従業員への教育・研修プログラムの整備:
ガイドラインを周知徹底するための研修や、生成AIに関する正しい知識を共有する機会を提供します。
などを通じて、企業が安心してAIを活用できる環境づくりをサポートしています。
参考ページ 日経BP「生成AIを業務で利用中の人が半数強に ビジネス展開は「5年後に3割突破」へ加速」
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください