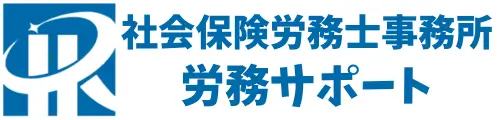【2029年10月~】すべての事業所が、社会保険強制加入?任意適用のメリットと手続き
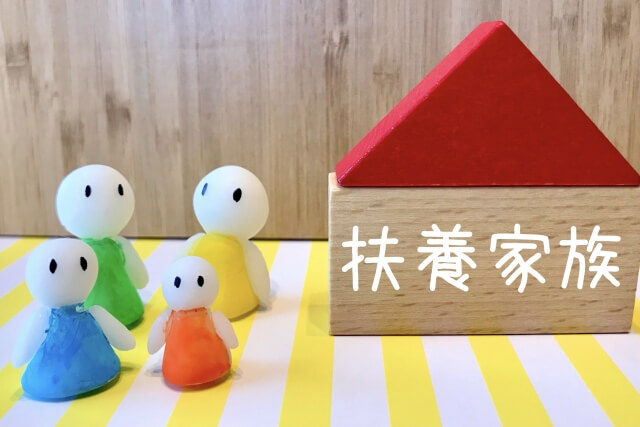
この度は、社会保険の任意適用についてご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。
社会保険労務士の視点から、社会保険の適用対象外となる個人事業所が
任意に社会保険に加入できる「任意適用」制度について
そのメリットと手続きを解説させていただきます。
任意適用とは?
本来、社会保険の加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)は
以下の要件を満たす事業所です。
- 法人の事業所
- 常時5人以上の従業員を雇用する特定17業種(製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、通信業、報道業、金融保険業、広告業、不動産業、物品販売業、理容美容業、健康保険組合・厚生年金基金等、教育研究業、医療業、士業など)の個人事業所
これに対し、上記強制適用事業所の要件に該当しない以下の個人事業所は
社会保険の適用対象外となります。
- 常時5人未満の従業員を雇用する個人事業所
- 特定17業種以外(農林水産業、サービス業の一部など)の個人事業所
しかし、これらの適用対象外の個人事業所でも、
「従業員の半数以上の同意」を得て
事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで
社会保険の任意適用事業所となることができます。
令和11年(2029年)10月からの変更点に注意!
現在、任意適用事業所とされる個人事業所の中には、
将来的に強制適用事業所に移行する可能性があります。
令和7年(2025年)の年金制度改正法により、2029年(令和11年)10月からは、
特定17業種の要件が撤廃となり、常時5人以上雇用している全ての個人事業所が
業種を問わず、原則として強制適用事業所となります。
この改正を機に、現在常時5人未満で雇用している事業所様や
常時5人以上雇用しているが特定17業種外のために任意適用事業所となっている事業所様は、
今後の社会保険の取り扱いについて、改めて検討することをおすすめします。
個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか(ご案内)
任意適用の最大のメリット
任意適用事業所となることで、事業主様と従業員様双方に大きなメリットが生まれます。
従業員様の保障と生活設計の充実
- 老後の年金が充実:
- 国民年金に加え、厚生年金保険に加入することで、将来受け取れる年金額が大幅に増加します。
国民年金のみの基礎年金に加え、報酬に比例した報酬比例の年金が上乗せされます。
- 国民年金に加え、厚生年金保険に加入することで、将来受け取れる年金額が大幅に増加します。
- 医療保険の保障が手厚くなる可能性:
- 健康保険に加入することで、国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられるようになります。
(ただし、国民健康保険でも自治体によっては独自の給付制度がある場合があります。)
- 健康保険に加入することで、国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられるようになります。
- 安心感と優秀な人材の確保:
- 充実した社会保険は、従業員様にとって大きな安心感につながり
定着率の向上や、優秀な人材の採用においても強力な武器となります。 - 週30時間以上働いている方の約6割が社会保険に加入できる求人は魅力的だと感じています
- 充実した社会保険は、従業員様にとって大きな安心感につながり
事例
社会保険料は、事業主と従業員が折半して負担します。
社会保険料の負担は発生しますが、福利厚生として従業員様に提供できる価値は非常に大きいといえます。
例えば、月収20万円の従業員Aさん(子二人扶養)は、
これまで国民健康保険・国民年金に加入し、月約37,800円を負担していました。
社会保険に加入すると、従業員、会社折半で、約28,300円の保険料を負担します。
さらに、老齢厚生年金が1年加入で約1,000円/月、終身で上乗せされ
休んだ4日目から約4,400円/日の傷病手当金が支給されます。
任意適用事業所となるための手続き
任意適用事業所となるためには、以下の手続きが必要です。
- 従業員の同意:
- 社会保険に加入する(任意適用事業所となる)ことについて、
その事業所で働く半数以上の従業員の書面による同意を得る必要があります。
- 社会保険に加入する(任意適用事業所となる)ことについて、
- 申請:
- 事業主が、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ「任意適用申請書」を提出します。
- 厚生労働大臣の認可:
- 審査を経て、厚生労働大臣の認可を受けると
その事業所は任意適用事業所となり、従業員は社会保険に加入します。 - 加入要件を満たす方全員が社会保険に加入することになりますので、ご注意ください。
- 審査を経て、厚生労働大臣の認可を受けると
社労士がサポートできること
任意適用は、従業員様の同意取得から申請手続き
その後の保険料計算や給与計算、社会保険加入後の各種手続きまで、専門的な知識を要します。
私ども社労士は、これらの一連の手続きを代行し
法的な側面から適切なアドバイスを提供することで、事業主様のご負担を軽減いたします。
貴社の働き方や雇用実態に合わせた
最適な社会保険の加入をご提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。