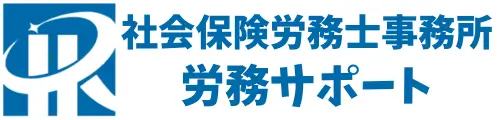ケガで働けなくても安心!「休業補償給付」とは?
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷や疾病により働けなくなった場合に
一定の給付を受けられる制度です。
ここでは、休業補償給付の要件や支給額、給付基礎日額、
待期期間、請求の仕方について解説します。
1.休業補償給付の3つの要件
休業補償給付を受けるためには、以下の3つの要件を満たし
賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付が支給されます。
- 業務上の負傷や疾病であること
労働者が業務に関連する事故や作業中の疾病などにより
働けなくなった場合に対象となります。 - 療養のために労働ができないこと
医師の診断などにより、仕事を続けることが困難と判断された場合が条件となります。 - 賃金が支払われていないこと
休業期間中に会社から賃金が支給されていない場合、給付を受けることができます。
2.支給額
休業補償給付は、給付基礎日額の60%が支給されます。
また、休業特別支給金(給付基礎日額の20%)も別途支給されます。
合計すると、休業期間中には給付基礎日額の80%が補償されることになります。
3.給付基礎日額
給付基礎日額は、労働者の休業前3ヶ月間の賃金総額を暦日数で割った額です。
具体的には、「過去3ヶ月の賃金 ÷ カレンダーの日数」 で計算されます。
例えば、直近3ヶ月の賃金総額が90万円、暦日数が90日の場合
給付基礎日額は 90万円 ÷ 90日 = 1万円 となります。
なお、賃金の総額には、ボーナスや臨時に支払われる賃金を除きます。
4.待期期間
休業補償給付には待期期間が設定されており、休業開始から3日間は給付の対象外です。
この期間については、会社が補償する場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
ただし、傷病やケガが治らず、支給開始から1年6ヶ月経過した日以後
傷病等級1級~3級に該当する場合には、「傷病補償年金」に切り替わります。
5.請求の仕方
休業が長期にわたる場合は、1か月ごとの請求が一般的です。
休業補償給付は、療養のため労働することができないため
賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。
その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、ご注意ください。
休業補償給付を受けるためには、以下の手順で申請します。
- 労働基準監督署へ提出
労働基準監督署へ書類を提出します。
休業補償給付を請求するときは、(様式第8号)を労働基準監督署に提出しましょう。
通勤災害の場合は、(様式第16号の6)になります。 - 審査・支給決定
労働基準監督署で審査が行われ、支給決定がされると給付が受けられます。
まとめ
休業補償給付は、業務上の負傷や疾病による休業時に労働者の生活を支える重要な制度です。
要件を満たし、適切に申請すれば給付基礎日額の80%が補償されるため
休業が必要な場合は早めに申請の準備を進めることが大切です。
社労士が解決いたします
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください